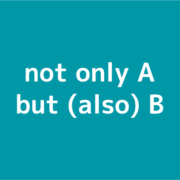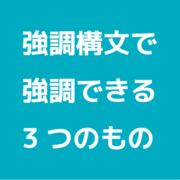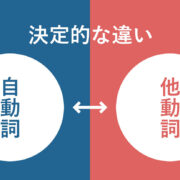not but 構文( not A but B )の意味と使い方|not only との違い
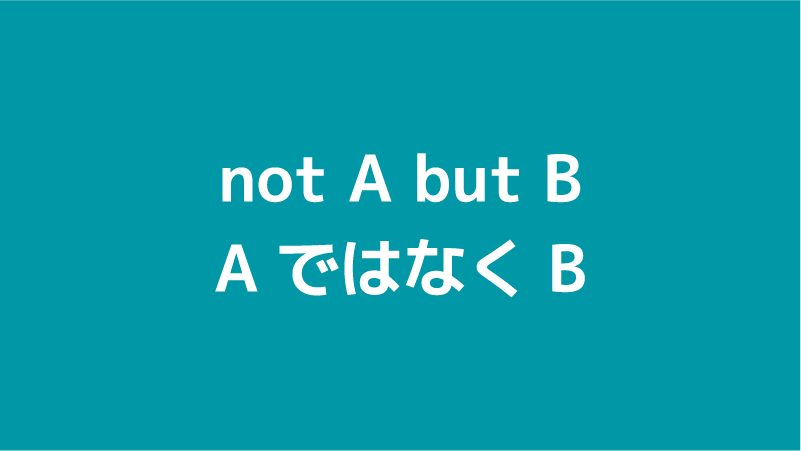
not A but B(AではなくB)は、中学校などでも出てくる基本的な表現なので、その意味を知っている人は比較的多いかもしれない。
ただ、AとBには必ずしも名詞がやってくる( not dogs but cats など)とは限らないので、場合によっては not but 構文だと見抜きにくいこともある。
そこでここでは、さまざまな例文を通して、not but 構文の使い方を整理していこう。
CONTENTS
not A but B の基本
not A but B(AではなくB)で使われる but は等位接続詞と呼ばれるものだ。
細かなことはさておき、等位接続詞は「同じ形」「同じ品詞」「似たような意味」を繋ぐ接続詞なので、not A but B を使うときには、AとBに同じ形・品詞を置くようにしよう。
→ AとBは同じ形・同じ品詞
My favorite animals are not dogs but cats.
(私が好きな動物は犬ではなく猫です。)
これを踏まえて、AとBにどんな形や品詞がくるのかという視点で、not A but B の使い方を整理していこう。
not A but B の3つの使い方
not A but B(AではなくB)には、次の3つの使い方がある。後半に進むにつれて not but 構文だと見抜きにくくなるので、丁寧に学んでいこう。
1.「単語」を繋ぐ
もっともわかりやすいのは、not A but B(AではなくB)が単語を繋いでる場合だ。
(私が好きな動物は犬ではなく猫です。)
(私は人生において金銭的な豊かさではなく心の平穏がほしい。)
(彼の答えは間違っていたのではなく正しかった。)
※副詞 rather(むしろ)を添えると強調した感じになる。
(彼らはそのプロジェクトにおいて、不注意というよりも慎重に働いた。)
※副詞 rather(むしろ)を添えると強調した感じになる。
(レストランでは走るのではなく歩きなさい。)
この場合、名詞と名詞が繋がれるだけでなく、形容詞と形容詞、副詞と副詞、動詞と動詞が繋がれることもあるというのは一つのポイントだ。
2.「句」を繋ぐ
not A but B(AではなくB)のAとBには「同じ形」「同じ品詞」がくればいいので、単語ではなく句(※)が繋がれることもある。前置詞句や不定詞がその代表だ。
※句:SVがない単語二語以上のカタマリ
(カバンの中ではなく、ソファの後ろで鍵を見つけた。)
(本当の美しさは、外見的な見た目ではなく、内面的なところにある。)
(彼の願いは去ることではなく留まることだった。)
この場合、not と but が少し離れるため、not but 構文だと気付きにくいかもしれないが、大きな形としては not dogs but cats と変わらない。
3.「節」を繋ぐ
また、場合によっては、not A but B(AではなくB)のAとBに節(※)がくることもある。
※節:SVがある単語二語以上のカタマリ
(彼女が彼を好きなのは、イケメンだからではなく、誠実だからだ。)
ここも not と but が少し離れるため、not but 構文だと気付きにくいかもしれないが、大きな形としては not A but B になっている。
補足|not が前に回ることもある
補足として、英語では not は動詞Vを修飾する(否定する)傾向が強いので、not A but B の not が do not ... / does not ... の位置にやってくることもある。
= I don't want riches but peace in my life.
(私は人生において金銭的な豊かさではなく心の平穏がほしい。)
= True beauty does not consist in external appearances but in inner qualities.
(本当の美しさは、外見的な見た目ではなく、内面的なところにある。)
この場合も not but 構文だと気付きにくくなるので注意しよう。
not only A but also B との違い
なお、not A but B(AではなくB)がAを否定した上でBを強調する表現であるのに対して、not only A but also B(AだけでなくBも)はAを肯定した上でBを強調する表現だ。
also が省略されたり、副詞の only が同じ意味の just, merely, simply になったりすると、両者の違いがわかりにくくなるので気を付けよう。
発展|強調構文 × not A but B
なお、not A but B(AではなくB)は強調構文と呼ばれる表現と組み合わさることもある。
(何を言うかではなく、どのように言うのかが重要だ。)
↓ 主語Sになっている not A but B を強調すると……
(重要なのは、何を言うかではなく、どのように言うのかだ。)
※強調構文では it is ... that の間に強調したい言葉(主語S・他動詞の目的語O・副詞)を置く。
強調構文については、必要に応じて以下のページで学んでおこう。
さいごに|英文法は「品詞」に注目して学ぼう
ここでは not but 構文( not A but B )の意味と使い方について、AとBの品詞や形に注目しながら学んだ。
not but 構文に限らず、品詞の働きを理解すると、英文法(語順のルール)がすごく楽になる。
中でも「自動詞と他動詞の違い」は英文法が身に付くかどうかの最初の分かれ道なので、やり残しがあれば優先的に学んでおこう。
オススメの関連記事