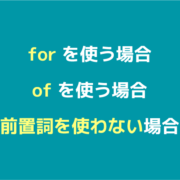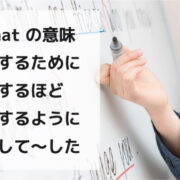【例文満載】too … to 構文の意味と使い方|so that への書き換えは?
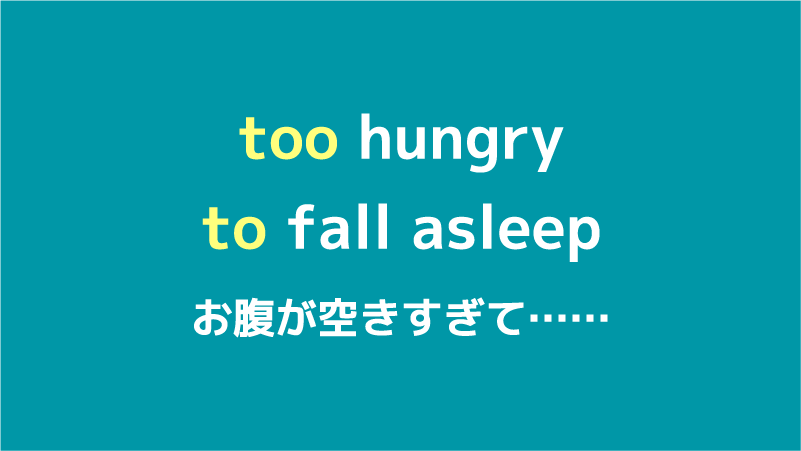
too … to 構文は「…すぎて~できない」「~するには…すぎる」といった否定的な意味の表現で、形容詞や副詞の程度を表すときに使うものだ。
ここでは、too … to 構文の使い方や注意点、また、似たような意味を持つ so that 構文への書き換えなどについて、例文を交えて学んでいこう。
なお、enough to との違いについては、以下のページで詳しく解説しているので、必要に応じて学んでおこう。
この記事を読んで得られること
- too … to 構文の使い方がわかる
- so that 構文への書き換えと注意点がわかる
CONTENTS
例文で確認! too … to 構文の使い方
too … to 構文は「…すぎて~できない」「~するには…すぎる」といった否定的な意味を持ち、形容詞や副詞の程度を表す表現だ。
不定詞の中が否定的な意味(〜できない)になっているところに注目しながら、例文をいくつか見てみよう。
[訳し下げ]お腹が空きすぎてすぐには寝られないよ。
[訳し上げ]今すぐには寝られないほどお腹が空いている。
[訳し下げ]湖の氷は薄すぎてスケートはできないよ。
[訳し上げ]湖の氷はスケートをするには薄すぎる。
[訳し下げ]私のことはリーと呼んでください。私の名前は複雑すぎて発音できないので。
[訳し上げ]私の名前は発音するには複雑すぎるので、私のことはリーと呼んでください。
[訳し下げ]そのスーツケースは重すぎて上の階へ持って行けない。
[訳し上げ]そのスーツケースは上の階へ持って行けないほど重い。
[訳し下げ]このスープ、熱すぎてすぐには飲めないよ。
[訳し上げ]このスープはすぐに飲むには熱すぎる。
このように、too … to 構文では、不定詞が表している動作が否定的な意味(〜できない)になる。
too は否定的な意味の言葉!?
ちなみに、いわゆる否定語( not や never )がないのに too … to 構文が否定的な意味になるのは、副詞の too(…すぎる)が否定的な気持ちから出る言葉だからだ。
too hungry(腹ペコすぎる)
too thin(薄すぎる)
too complicated(複雑すぎる)
こうした表現には、すべて否定的なニュアンスが感じられるだろう。副詞の too(…すぎる)は「強調」と「否定」の2つの気持ちを宿した言葉だということだ。
too … to 構文を使うときの2つの注意点
too … to 構文を使うときには、次の2つのポイントに注意しよう。
1. 意味上の主語は to の前に置く
不定詞の意味上の主語(不定詞が表している動作を行う主語)が「文頭の主語」や「世間一般の人々( we, you, people など)」と異なる場合には、to の前に “for + A” という形で表現しよう。
(その仕事は彼が扱うには少々大きすぎる。)
※ to handle の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for him という形で表す。
(そのケーキは甘すぎて、彼女は完食できなかった。)
※ to handle の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for her という形で表す。
(この専門書は初心者が理解するには難しすぎる。)
※ to understand の意味上の主語が「文頭の主語」でも「世間一般の人々」でもないので、for a beginner という形で表す。
too ... to 構文に限らず、意味上の主語を “for + A” という形で表すのは、一般の不定詞でも同様なので、しっかりと押さえておこう。
2. 目的語Oが文頭の主語と同じなら表現しない
ここは too … to 構文を使うときに特に注意すべきところだ。
英語では「形容詞を修飾する to do(副詞的用法の不定詞)の目的語Oが文頭の主語Sと同じ場合には、目的語Oを表現しない」という傾向がある。
too … to 構文は副詞的用法の不定詞を使った表現で、このパターンに当たる。そのため、不定詞の中の目的語Oが文頭の主語Sと同じ場合には、それを表現しない。
The ice on the lake is too thin to skate on it.(×)
Please call me Lea because my name is too complicated to pronounce it.(×)
The job is a little too large for him to handle it.(×)
「英語では日本語と違って目的語Oをとても大切にする」という大原則に反する例外なので、ここはしっかりと押さえておこう。
so that 構文への書き換え
さて、too … to 構文のように、形容詞や副詞の程度(~するほど…だ)を表す表現は他にもある。代表的なのは so that 構文だ。
書き換えるときの注意点は、「否定語 not 」と「目的語」をしっかりと表現するというところだ。
= The ice on the lake is so thin that we (you) can not skate on it.
※目的語Oは原則、表現する。too … to 構文が例外。
※「強調+否定」の意味を持つ too が「強調の so 」と「否定の not 」に分かれた感じ。
= The job is so large that he can not handle it.
※目的語Oは原則、表現する。too … to 構文が例外。
※「強調+否定」の意味を持つ too が「強調の so 」と「否定の not 」に分かれた感じ。
なお、so that 構文には全部で4つの意味がある。必要があれば以下のページで学んでおこう。
さいごに|too … to 構文は否定的な意味の表現
too … to 構文では、
・意味上の主語は “for + A” という形で to の前に置く
・目的語Oが文頭の主語と同じなら表現しない
ということを押さえておこう。
オススメの関連記事