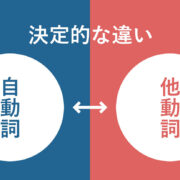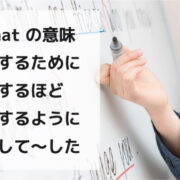間接疑問文とは? 作り方・使い方をわかりやすく学ぼう
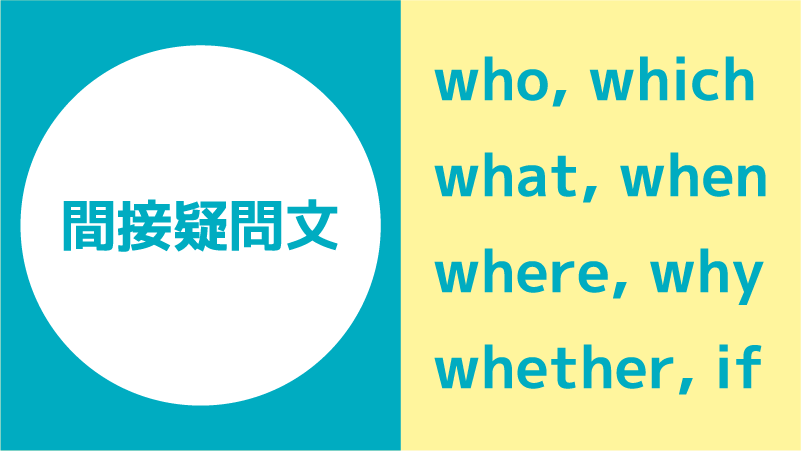
間接疑問文とは、普通の疑問文(「?」で終わる疑問文)を名詞化した表現のことで、who や where といった疑問詞を使ったものと、接続詞の whether や if(〜するかどうか)を使ったものの2種類がある。
ここでは、間接疑問文の作り方や使い方について、具体的な例文を交えながら学んでいこう。
CONTENTS
間接疑問文とは?
間接疑問文は、普通の疑問文(「?」で終わる疑問文)を名詞化した表現だ。
あえて日本語で説明するなら、「どこに住んでるの?」というのが普通の疑問文であるのに対して、「どこに住んでいるかということ」という表現が、英語での間接疑問文に当たる。
「どこに住んでるの?」
↓ この疑問文を名詞化すると、例えば……
Where you live doesn’t matter.
「あなたがどこに住んでいるかということ」は重要ではない。
※ “Where you live” が間接疑問文で、ここでは文の主語Sになっている。
このように、間接疑問文は名詞節(名詞のカタマリ)として使われる。
間接疑問文は「疑問文の意味を持つ名詞節」だと押さえておこう。
間接疑問文の作り方
普通の疑問文と間接疑問文とでは、語順や使う単語が少し違ってくる。
普通の疑問文には、
・疑問詞を使った疑問文
・疑問詞を使っていない疑問文
の2種類があるので、それぞれの場合に分けて、間接疑問文の作り方を見てみよう。
1. 疑問詞がある場合
疑問詞( who, which, what, when, where, why, how )がある疑問文の内容を間接疑問文として表現する場合には、「疑問詞 +SV」という語順にしよう。
要は、疑問文の語順を解消するということだ。
(彼は誰を愛しているの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
I’m wondering who he loves.
(彼は誰を愛してるんだろう。)
※間接疑問文は “who he loves” の部分
(どちらを選びますか?)
↓ 間接疑問文にするなら……
It’s up to you which you choose.
(どちらを選ぶかはあなた次第だ。)
※間接疑問文は “which you choose” の部分
(これを解決するために何ができるだろう?)
↓ 間接疑問文にするなら……
I’m wondering what I can do to resolve this.
(これを解決するために何ができるだろう。)
※間接疑問文は “what I can do to resolve this” の部分
(雨はいつ降りますか?)
↓ 間接疑問文にするなら……
Do you know when it is going to rain?
(雨がいつ降るか知っていますか?)
※間接疑問文は “when it is going to rain” の部分
(彼はどこに住んでいるの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
Do you know where he lives?
(彼がどこに住んでいるか知っていますか?)
※間接疑問文は “where he lives” の部分
(どうしてそんなに悲しいの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
I would like to understand why you feel so sad.
(あなたがどうしてそんなに悲しんでいるのか、理解したいんです。)
※間接疑問文は “why you feel so sad” の部分
(どうやって体重を保っているの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
Tell me your secret on how you keep your weight down.
(どうやって体重を保っているのかについての秘密を教えてよ。)
※間接疑問文は “how you keep your weight down” の部分
補足:疑問詞が主語Sの場合
なお、疑問詞そのものが主語Sになっている場合には、普通の疑問文も間接疑問文も、どちらも「疑問詞 + V」という語順になる。
(誰が彼にそれをするように言ったんだろう?)
↓ 間接疑問文にするなら……
I don’t know who told him to do that.
(誰が彼にそれをするように言ったかわからない。)
※間接疑問文は “who told him to do that” の部分
(どちらが良い選択だろう?)
↓ 間接疑問文にするなら……
It is difficult to decide which is the better choice.
(どちらがより良い選択なのかを決めるのは難しい。)
※間接疑問文は “which is the better choice” の部分
2. 疑問詞がない場合
一方で、疑問詞がない疑問文の内容を間接疑問文として表現する場合は、接続詞の whether や if(〜するかどうか)を使う。
ここでも、疑問文の語順は解消して、「 whether/if + SV 」という語順にしておこう。
(彼は嘘をついているの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
I don’t know whether/if he is lying.
(彼が嘘をついているかどうかわからない。)
※間接疑問文は “whether/if he is lying” の部分
(彼の愛を受け入れるの?)
↓ 間接疑問文にするなら……
It's up to you whether/if you accept his love.
(彼の愛を受け入れるのかどうかはあなた次第だ。)
※間接疑問文は “whether/if you accept his love” の部分
間接疑問文の使い方
間接疑問文は「疑問文の意味を持つ名詞節」なので、名詞が置かれるところに表現しよう。
1. 主語Sとして
(誰と結婚するかは将来に影響する。)
・間接疑問文 “Whom you marry” が主語S
2. 補語Cとして
(もっとも重要なことは、あなたがどこへ向かおうとしているかだ。)
・間接疑問文 “where you're going” が補語C
3. 他動詞の目的語Oとして
(どんな問題を抱えているのか教えてください。)
・間接疑問文 “what problem you have” が他動詞 know の目的語O
4. 前置詞の目的語Oとして
(ソーシャルメディアを眺めることにどれほどの時間を使っているかを考えてみよう。)
・間接疑問文 “how many hours you spend scrolling social media” が前置詞 about の目的語O
5. 同格修飾の修飾語Mとして
名詞には「前の名詞を同格的に修飾する」という働きもあるが、間接疑問文が他の名詞を同格的に修飾する修飾語Mとして使われることはあまりない。
なお、そもそもの名詞の使い方については、以下のページで学ぶことができる。
補足(発展):whether と if の違い
間接疑問文を作る whether と if は、どちらも「〜するかどうか」という意味の接続詞だが、whether の方が使い勝手がいいと押さえておこう。
“if SV(SがVするかどうか)” という名詞節は、
・文頭の主語S
・前置詞の目的語O
・同格修飾の修飾語M
にはなれないからだ。
間接疑問文の例文まとめ
間接疑問文を使った例文については、以下のページにまとめているので、必要に応じて参考にしてほしい。
まとめ「間接疑問文は名詞節」
ここでは間接疑問文の作り方や使い方について学んだ。
英文法(語順のルール)という点で見れば、「間接疑問文は名詞節」というところが大きなポイントなので、よく押さえておこう。
オススメの関連記事